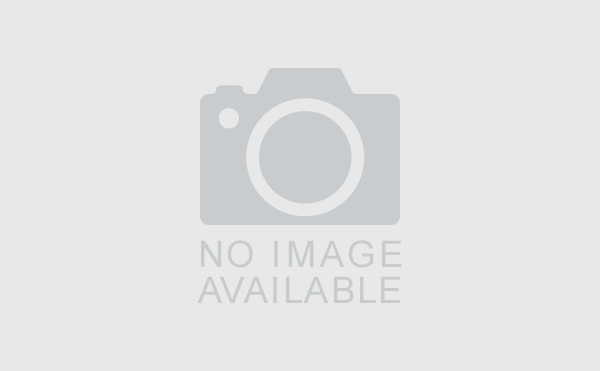袋井市観光協会は、江戸時代に書かれた文献をもとに「たまごふわふわ」を復元して、町おこしに活用しています。復元されたたまごふわふわは、だし汁の中に泡立てたメレンゲが浮かんでいるような、本当に食感がふわふわな料理です。
現在は5軒の飲食店のメニューに載っています。東海道から袋井駅にかけての近辺では、3軒のお店で食べることができます。
どまん中 0538-43-8858
遠州味処 とりや茶屋 0538-42-2427
山梨屋 0538-42-2422
※営業時間や休日、入店可能人数などについては、直接お店にお問い合わせください。
袋井市観光協会の会員さんが江戸時代の旅日記「升屋平右衛門仙台下向日記」に、袋井宿での宿泊時の朝食に「玉子ふわふわ」と書かれているのを見つけ、やはり江戸時代の書物にあったレシピをもとに復元して、これらのお店で出されるようになったそうです。

大坂の豪商升屋平右衛門が、蔵元を務める伊達家の国元である仙台に向かう途上で書いた日記です。袋井宿に宿泊したのは文政10年1月25日から26日にかけて。脇本陣の太田屋に宿泊しています。26日の朝食についての記載の中に「皿 玉子 ふわふわ」と記載されていました。
私も袋井でいただいたことがあるのですが、まさに泡立てたメレンゲのふわふわな食感ですが、味は黄身を含んだ玉子の味です。他の卵料理と比較すると、味は茶碗蒸しとよく似ています。
そんなたまごふわふわですが、実は・・・
袋井の郷土料理ではなかったのです!
戦国時代ころまで、仏教の不殺生戒のために卵を食べることはめったにありませんでした。それが江戸時代になると卵が広く食べられるようになりました。戦国時代末期にヨーロッパ人が渡来したことで、卵を食べる習慣が日本に広まったという説があります。
そのため江戸時代には卵料理のレシピが多くの文献に残されているのです。
古くは寛永3年(1626)に後水尾天皇が二条城に行幸したときの献立にも載っているのですが、この献立についてはいろいろ問題がありまして、幕府が記録した献立が世間に出たとされているのですが、それを見た人たちが過去の事例からして「こうに違いない」と手を加えた形跡があるのです。現に私がインターネットや図書館で探した献立は、それぞれすこしずつ内容がちがうものでした。
例えば昭和11年発行の「祭礼料理考」という本には「大猷院様行幸二條御城御献立」という項目があり、寛永3年の後水尾天皇の行幸の際の料理の献立が載っています。そこに「吸物 フワフワ」と名称の料理があります。これが「たまごふわふわ」のことではないかと考えられます。
寛永20年(1643)に発行された「料理物語」にはたまごふわふわのレシピが載っており、溶いた卵にだし汁、醤油と酒を加えて固くならないように蒸かす、といった内容のことが書いてあります。ほかにも江戸時代の中期にかけて多くのレシピ本がありまして、醤油、酒を入れないとか、だし汁の量が異なるところがあるものの、作り方は概ね同じです。
これらのレシピは袋井に地域が限られたものではなく、前記のとおり京都二条城における行幸の折に出されていますし、久保田藩佐竹家の家老の旅日記「宇都宮孟綱旅中日記」にも、古河宿でたまごふわふわを食べたという記載があります。
たまごふわふわは、江戸時代に地域を問わず広く食べられていた料理だったと考えられます。東海道を歩いていると袋井宿の郷土料理だったような気がしてしまいますが、そうではなかったのです。
ところでたまごふわふわは、江戸時代の中期ころからレシピ本に登場しなくなります。人々の卵料理の好みが変わったのか、あるいは茶碗蒸しのようなものに変遷していったようなのです。
さて、文化10年(1813)の「升屋平右衛門仙台下向日記」、そして安政2年(1855)の「宇都宮孟綱旅中日記」はいずれも江戸時代も終わりちかいころに書かれたものです。ですから日記には「玉子ふわふわ」と記載されているものの、実際には江戸時代前記から中期にかけての「玉子ふわふわ」とはレシピの異なる玉子料理だった可能性があります。
もしかしたら、袋井市観光協会が「たまごふわふわ」を復元するきかっけとなった日記を記した升屋平右衛門、彼が食べた「玉子ふわふわ」とは、現在の茶碗蒸しに近いものだった可能性もあるのです。
今ではあまり例を見ない料理となったたまごふわふわ、いまや袋井でしか食べられませんので、ぜひ彼の地を訪れて体験してみてください。

(歩き旅応援舎代表 岡本永義)
参考文献
日本都市生活史料集成8 宿場町篇「升屋平右衛門山片重芳の文化十年仙台下向日記」
祭礼料理考「大猷院様行幸二條城御献立」
秋田県公文書館発行「古文書倶楽部 2012.11 第50号」
袋井市観光協会発行パンフレット「江戸時代の名物料理 袋井宿たまごふわふわ」
松本仲子「江戸時代の料理本にみるたまご料理について」
最新のブログ記事
- 京橋交差点東京都中央区には「京橋」という地名があります。 地名のもととなった場所がここ、現在は高速道路がありますが、ここには昭和34年(1959)まで川があり、橋が架けられていたのです。 その橋の名前が京橋です。 東海道の歩き旅を […]
- 中橋広小路日本橋を出発して東海道(第3京浜)を少し南に下ると、日本橋三丁目の交差点に出ます。右手の奥には、東京駅の八重洲口が見えます。 交差点には平和の鐘があります。 ヤン・ヨーステンの像があります。 この像に関しては、他の記事が […]
- 京橋の親柱日本橋から東海道の歩き旅に出ると、最初に出会う橋が京橋です。高速道路が架かる交差点、ここが京橋の跡地になります。 高速道路の下には、かつて橋がありました。昭和38年(1963)から40年にかけて、下を流れていた京橋川が埋 […]
- ヤン・ヨーステンと八重洲の物語東海道の歩き旅を楽しむとき、日本橋から歩き始める人が多いように思います。歩き始めて比較的すぐに到達するのが日本橋三丁目の交差点です。 東海道と八重洲通りが交差するこの交差点に、ある人物の像があります。 慶長5年(1600 […]
- 日本橋の擬宝珠今日も日本橋のお話です。東海道五十三次を歩いて京都へ旅しようとするときの出発点である日本橋ですが、あっさり出発してしまうことも多く、あまり日本橋について語られることはありません。でも日本橋って、ネタの宝庫なんですよ。 現 […]
- 東京市道路元標日本橋は歩き旅応援舎における東海道の歩き旅イベントの出発点であり、古地図散歩のコースでもたびたび立ち寄ることで、たいへんお馴染みの場所です。 この日本橋の北詰に「元標の広場」と呼ばれる場所があります。そこに「東京市道路元 […]
- 日本橋のまん中で日本橋です。 歩き旅応援舎では、東海道の歩き旅の出発点として、あるいは古地図を見ながらの町歩きで立ち寄る場所としてお馴染みです。 日本橋は、徳川家康が初めて架けて以来、日本の道路の中心ということになっています。 現在も地 […]
- 京橋の灯台?! 第一相互館東海道を日本橋から歩き始めた場合、京橋はすでに見えています。高速道路の高架があるので、すぐにわかります。 写真ではわかりにくいのですが、実際に日本橋に行けばすぐにわかります。ずっと向こうの方に高速道路の高架が見えてます。 […]
- 日本橋・歴史の“傷痕”東海道の歩き旅の出発点でもあり、古地図散歩でもたびたび訪れている日本橋。この橋は慶長8年(1603)に初めて架けられたとされています。いまからおよそ420年も前のことです。 現在の橋に架け替わったのが明治44年(1911 […]
- あいつのせいで鎌倉へ ー十六夜日記秘話ー東海道を旅して小夜の中山峠を越えるとき、蓮生法師の歌碑があります。 蓮生法師は俗名を宇都宮頼綱といい、もとは鎌倉の御家人でしたが和歌を得意とし、出家して京都に移り住んだ人物です。これについては以前のブログに書きました。 […]
東海道歩きイベント開催中
このブログを書いたスタッフと東海道を歩きませんか? 途中から、あるいは一部だけでもご参加いただけます。参加したいイベントをクリックしてください。リンク先にお申し込みフォームがあります。
- 京都まであるく東海道 第8期 磐田~国府開催日 10月5日(土)~10月6日(日) 磐田~高塚 11月2日(土)~11月3日(日) 高塚~二川宿 12月7日(土)~12月8日(日) 二川宿~国府 開催時間 1日目 10:30~16:30ころ2日 […]
- 日帰りであるく東海道 第3期 大磯宿~国府津開催日時 10月26日(土)9:00~17:00 大磯宿~国府津 5月25日(土)の藤沢宿~茅ヶ崎、6月22日(土)の茅ヶ崎~大磯宿は、お申し込みの受付を終了しました。 ※終了時間は進行状況に応じて大きくずれる可 […]