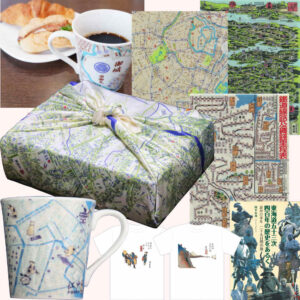東海道を歩いて京都へ向かい、桑名に上陸すると(とはいっても、現在は船ではなく電車で桑名に行きますが)、伊勢路には大福餅が細長いという食文化があります。
これはどうやら伊勢神宮へといたる伊勢街道(日永で東海道から分かれて伊勢神宮にむかいます)沿いの大福餅の文化らしいのです。
なぜ細長いのかについては、以前に東海道四日市宿資料館で聞いたことがあります。

「歩きながら食べやすいからじゃないですかねえ」
こういう言い方でしたから、資料館の方の感想的な色合いが強そうなのですが、確かに細長い餅は食べ歩きにぴったりです。食べてみればわかりますが、丸い大福餅は口の周りが粉だらけ餡子だらけになりますので、その顔で街道を歩くのはちょっと恥ずかしいです。
そこで食べ歩きにぴったりの伊勢の細長い餅を買いに行きました!

食べ歩くための条件として、ばら売りをしてくれるということがあります。お店を出たら、即刻もぐもぐ食べることができます。
そんな細ながいお餅を求めて、まずは桑名へ!
桑名には「安永餅」という名のお餅を売っているお店が2軒あります。まずは桑名駅の東口を出たら右手にある安永餅の柏屋さんへ。
柏屋さんの餅の特徴は、店で餅をひとつずつ職人さんが作っているところ。そして食べ歩きをしやすいように、紙に乗せただけの状態でも買うことができることです。
安永餅を売っている2軒のお店は、いずれも東海道の桑名宿から四日市宿の間にあった安永の立場で旅人たちに餅を供していた茶屋が起源だそうです。
鉄道ができたことで、駅の近くにお店を移したのだとか。
さて、肝心の餅ですが、お店の方が「すぐ食べるんでしたら、熱々のものがありますよ」と出来たてのお餅を出してくれました。

伊勢の細長い大福餅は、餡の入った細長い餅を火で炙ったものです。だから出来たては熱々(とはいっても温かいくらいでした)なのです。でこぼこの外観とまだらな焼き目が、いかにも1つずつ手作りです。
大きさは長さ12.5センチ、幅3.1センチ。たしかに細長いです。
食感はやわらかく、焼き目が香ばしく、優しい甘さでした。子供のころに自宅で作ったあんころ餅を、焼いて食べたときのことを思い出しました。そういえば、大人になってからは餅は買って食べる様になったので、自宅で作ったことはないなあ。
次のお餅も桑名駅の近くにあります。
こちらのお店は永餅屋老舗。餅の形は表面がなめらかなきれいな平らで、焼き目も全体的に均一についています。機械で作っているのでしょうか?

(餅の写真)
大きさは長さ13.0センチ、幅3.0~3.2センチ。今回試したお餅の中では一番細長いです。
食感は見た目のとおりなめらかなものでした。
安永餅老舗では、紅白のお餅を売っています。ただしお店の人によれば、紅いものはいつもあるわけではないそうです。
次のお店は四日市市です。電車で移動して、JR四日市駅の近くです。
四日市は港町です。江戸時代から商業港として栄えていました。その港から旧宿場町に向かってアーケードがつづいています。
そしてアーケードの途中にはこんな看板が。

このアーケードの一角、駅のすぐ近くに細長い餅のお店、金勝軒があります。
このお店の餅の名前は太白永餅。もともとは東海道の日永の立場で売られていたのだそうです。ある日この餅を食べた漢学者が、日永立場の永餅の中で一番おいしいということで、漢語で一番を意味する「太白」を餅の名前に付けたのだと伝わっています。
ここのお餅も1つ1つ手作りらしく、見た目はでこぼこで焼き目もまばらです。

大きさは長さ11.8センチ、幅4.0センチ。今回試した餅の中ではこれでも一番ずんぐりしています。
食感は、まずは焼き目が香ばしいこと、そして幅があるだけ歯ごたえがあります。
さて、次の餅を求めて、今度は鈴鹿に移動します。鈴鹿市内の伊勢街道沿いに、細長い餅のお店があるのです。
そのお餅の名は立石餅。石でできた道標の前で売られていたから「立石」だと聞いたことがあります。
道を歩きながら、どこかで見た風景だなあと思ったら、以前に神戸城を見に来たときに通ったことがある道でした。
東海道関宿に、織田信長の三男、織田信孝の墓があります。

本能寺の変の後、織田家の跡目争いに敗れて死んでいった武将です。武勇で知られた神戸城の豪族神戸具盛の養子となり、神戸信孝を名乗っていました。そこで神戸城を見に来たことがあったのです。

東海道を案内しようと思うと、東海道を歩いただけでは足りないところがありまして、関連するいろんなところを見に行くのです。
さて、以前に来た伊勢街道を歩いて立石餅のお店、もち久へとやってきました。

なんと休み!
Googleが火曜日定休というから水曜日に来たのに、なんと休み!
Google、ゆるさん!!
立石餅を試すのはまたの機会に譲ることにします。
ちなみに鈴鹿市は大黒屋光太夫の出身地。市役所には光太夫の洋装の銅像がありました。

みなさんも東海道を歩くとき、ぜひ細ながい餅の食べ歩きをお勧めします。特に桑名駅を降りたら目の前の柏屋さん、作りたてが食べられてお勧めです。
(歩き旅応援舎代表 岡本永義)
その他のブログ記事
- 能登半島地震にかかる義援金について
- 「たまごふわふわ」の正体!
- たまごふわふわ? ふわふわたまご?
- 駐車場には弁財天
- 日本の地下鉄の夜明け 対立編
- 日本の地下鉄の夜明け 開業編
- 10周年 長かったような、あっという間のような
- 2023年を振り返って
- 東海道を案内して嬉しかったこと