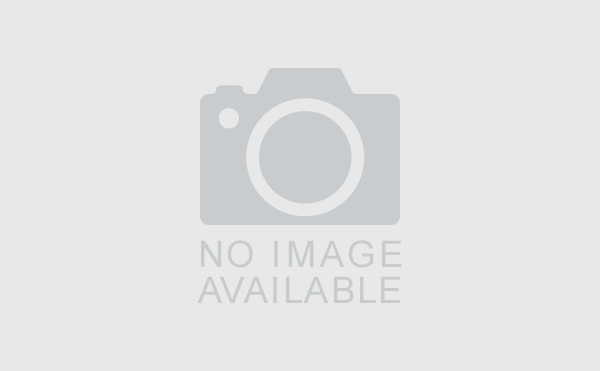当舎で東海道をご案内している「日帰りであるく東海道」」「京都まであるく東海道」ですが、2020年7月に日本橋を出発した第4シリーズが、まもなく三条大橋に到達しようとしています。

夏の間の3か月のお休みをはさんで、10月21日に土山宿から「京都まであるく東海道」は再開しました。なお、写真に写っている人たちは、私と一緒に歩いているお客様です。また、当日以外の日に撮影した写真を一部に含みます。
土山宿、古い建物がたくさんあります。

そしてコスモスがきれいです。

土山は茶の産地です。
土山茶の始まりは、常明寺の鈍翁和尚が京都の大徳寺から茶の実を持ち帰ったことです。この実から木を育て、寺で飲用に用いたのが始まりとされています。

茶が土山の名物となったのは、永雲寺の天嶺和尚がこれもやはり大徳寺から茶の実を持ち帰り、ここから育てた木から茶を作り、街道沿いで旅人たちに分け与えたことです。

この茶の製法を北土山の庄屋だった松山佐平治が引き継ぎ、土山宿の土産品として売り出したことから、茶が土山宿の名物となったのです。

土山宿から水口宿までの間は、かつてとあまり道幅の変わっていない東海道が残っています。
酒蔵あります。

道標あります。

川もあります。

そして土山宿から水口宿の間には、伊勢神宮が創建されるにいたる伝説が残っています。
この甲可日雲宮は小さな神社ですが、朝廷内に安置されていた天照大神の依代を新たに安置する場所を探す旅に出た倭姫が、伊勢にその場所を見つける途中に4年間滞在したと伝わる神社です。

そして1日目は水口宿に到着して終了しました。

水口宿は城下町です。
江戸時代に水口藩の城下町だっただけではなく、それ以前の安土桃山時代には宿場の北の山に水口岡山城がありました。
水口は東海道に2箇所しかない道が三筋に分かれた宿場の1つです。

この3筋の道をじっくりとめぐります。
連子格子、馬つなぎ輪、ヴォーリズ建築など、なかなか見応えがある宿場です。



曳山も見学させていただきました。

水口宿を出ると、一直線の道がつづきます。北脇畷です。

この一直線の道の先にあるのは・・・

高さ10mの巨大な常夜灯。野洲川(横田川)にある横田の渡し場の跡です。
渡し場跡に至る途中にあるのは・・・

植城跡。甲賀武士の城です。
土塁が残っています。細い溝は水濠の跡です。

ここの支配者山中氏は、関ヶ原合戦に先立つ伏見城攻防戦で徳川軍の援軍として城に籠もり全員討ち死にしています。
彼らの遺族は甲賀組として徳川家の御家人となり、子孫が里帰りをしたときに建てた戦死者の墓が残っています。

野洲川を渡って先に進みます。左手に見える山は三雲城の跡です。

岩が多い山です。巨岩の八丈岩は東海道からもよく見えます。

ここには「鬼滅の刃」に出てくる岩のモデルと言われている割れた丸岩もありまして、行きはしなかったものの写真でご紹介しました。

そしてこのトンネル。

トンネルの上、実は川だったんです。地面よりも水面が高い川のことを天井川といいます。水口から石部宿にかけては、天井川が多かった地域です。
天井川はいったん堤防が決壊すると一気に水が流れ落ちて危険なため、川を付け替える工事が進められていて、現在ではトンネルの上を川が流れているところはなくなりました。

でも、トンネルの上が川だったなんて、びっくりです!
石部宿に着きました。静かなたたずまいです。

本陣の跡には、今も本陣家の人たちが住んでいます。

今回は石部駅で終了しました。石部駅、建て直し工事中です。新しいきれいな駅になりそうです。

今回歩いた土山宿から石部宿は、ほとんどの場所がかつての東海道の道幅で、瓦屋根の木造住宅が多く、旧街道の風情が濃厚な区間でした。
次回は石部宿を出発し、草津宿で一泊して石山駅まで。次々回は石山駅を出発し、大津宿で一泊していよいよ三条大橋へ。
三条大橋到達のことを考えると気持ちが高ぶるのと同時に、これで旅が終わってしまうのかという寂しさを感じてしまいます。
(歩き旅応援舎代表 岡本永義)
最新のブログ記事
- 中橋広小路日本橋を出発して東海道(第3京浜)を少し南に下ると、日本橋三丁目の交差点に出ます。右手の奥には、東京駅の八重洲口が見えます。 交差点には平和の鐘があります。 ヤン・ヨーステンの像があります。 この像に関しては、他の記事が […]
- 京橋の親柱日本橋から東海道の歩き旅に出ると、最初に出会う橋が京橋です。高速道路が架かる交差点、ここが京橋の跡地になります。 高速道路の下には、かつて橋がありました。昭和38年(1963)から40年にかけて、下を流れていた京橋川が埋 […]
- ヤン・ヨーステンと八重洲の物語東海道の歩き旅を楽しむとき、日本橋から歩き始める人が多いように思います。歩き始めて比較的すぐに到達するのが日本橋三丁目の交差点です。 東海道と八重洲通りが交差するこの交差点に、ある人物の像があります。 慶長5年(1600 […]
- 日本橋の擬宝珠今日も日本橋のお話です。東海道五十三次を歩いて京都へ旅しようとするときの出発点である日本橋ですが、あっさり出発してしまうことも多く、あまり日本橋について語られることはありません。でも日本橋って、ネタの宝庫なんですよ。 現 […]
- 東京市道路元標日本橋は歩き旅応援舎における東海道の歩き旅イベントの出発点であり、古地図散歩のコースでもたびたび立ち寄ることで、たいへんお馴染みの場所です。 この日本橋の北詰に「元標の広場」と呼ばれる場所があります。そこに「東京市道路元 […]
- 日本橋のまん中で日本橋です。 歩き旅応援舎では、東海道の歩き旅の出発点として、あるいは古地図を見ながらの町歩きで立ち寄る場所としてお馴染みです。 日本橋は、徳川家康が初めて架けて以来、日本の道路の中心ということになっています。 現在も地 […]
- 京橋の灯台?! 第一相互館東海道を日本橋から歩き始めた場合、京橋はすでに見えています。高速道路の高架があるので、すぐにわかります。 写真ではわかりにくいのですが、実際に日本橋に行けばすぐにわかります。ずっと向こうの方に高速道路の高架が見えてます。 […]
- 日本橋・歴史の“傷痕”東海道の歩き旅の出発点でもあり、古地図散歩でもたびたび訪れている日本橋。この橋は慶長8年(1603)に初めて架けられたとされています。いまからおよそ420年も前のことです。 現在の橋に架け替わったのが明治44年(1911 […]
- あいつのせいで鎌倉へ ー十六夜日記秘話ー東海道を旅して小夜の中山峠を越えるとき、蓮生法師の歌碑があります。 蓮生法師は俗名を宇都宮頼綱といい、もとは鎌倉の御家人でしたが和歌を得意とし、出家して京都に移り住んだ人物です。これについては以前のブログに書きました。 […]
- 二人の蓮生法師「平家物語」の一ノ谷合戦のくだりで知られる熊谷直実は、後に出家して蓮生と名乗りました。 武勇の人だった直実らしく、出家後を描いた浮世絵もこんな感じです。 絵師に悪意を感じちゃうくらい「武勇な」お坊さんに描かれています。 […]